
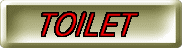

このページでは、ハムスターのケージに設置する トイレ容器 について考えていることを記します。
| 1. | トイレは必要? | ||
| (1) | 尿の処理は重要 | ||
| (2) | 決まった場所にしても安心できない | ||
| (3) | 掘れる場所が必要 | ||
| 2. | 容器にはどんなものを使うか? | ||
| (1) | 大きさはどのくらいがよい? | ||
| (2) | 形はどんなものがよいか | ||
| 3. | 砂にはどんなものを使うか | ||
| (1) | 紙製の砂はどうか? | ||
| (2) | 木製の砂はどうか? | ||
| (3) | 鉱物性の砂は? | ||
| (4) | なぜシリカゲルか? | ||
| (5) | 砂の粒度は? | ||
| 4. | ドワーフ種の場合は? | ||
| 5. | トイレを覚えてもらうには・・? | ||
| (1) | 設置場所は? | ||
| (2) | すぐに覚えてくれない? | ||
「トイレは必要ない」という人も居ます。また、置くなと指導する獣医師もいます。 しかし、以下に示すような理由から、うちではトイレを設置していますし、また、トイレはおいた方が良いだろうと思っています。
(1)ハムスターにとって尿の処理は糞の処理より重要である
ハムスターは乾燥地帯の生き物です。言うまでもなく、巣に限らず住環境が湿度の低い状態に保たれるのが良いです。
ハムスターの住環境で、湿度の上昇の原因となるものを考えると、飲み水と尿が考えられます。 飲み水はハムスターにとって必要なものであり、ボトルで与えない場合でも、毎日野菜を与えるなどの方法でかならず補給されるべきものなので、これに手を着けることはできないでしょう。 次に尿ですが、これも、取り除くのは難しく、ハムスターに水分をとらせる限りは必ず排泄されるものです。
しかし、尿については、トイレの場所を特定し、その場で処理してしまうことで、その影響を最低限に留めることもできます。 尿がトイレで処理されても、糞は好きなところでするというのは正解ですが、だからトイレがあっても仕方ないのではありません。 尿の場合には汚れたものがあるからだけいけないのではなく、それに触れたものが湿っていることもいけないのです。
(2)決まった場所にしても安心できない
よく、ハムスターは決まった場所に用を足すから、トイレ容器がなくても尿が拡散することはない、というようなものを見聞きしますが、すくなくともウッドチップやペーパーチップを敷き材として使っている環境ではこれは間違った認識です。
ハムスターは巣材になりそうなものや気に入ったものを巣に運び込んでしまいます。ウッドチップやペパーチップはハムスターにとって格好の巣材なのです。従って、ハムスターがトイレにしている場所近くのチップが巣材となって巣に運ばれることも少なくありません。
また、直接トイレとなっている場所のチップを運んでいないようでも、ハムスターが敷き材を掘り返すことで、湿った敷き材がケージや水槽中に拡散してしまうこともあり得るのです。
うちでは、敷き材を使っていませんが、そのかわりトイレ容器をもし置かなければ、トイレになった場所が常に濡れている(尿がたまっている)ようになってしまいます。
(3)掘れる場所が必要
本質的にはトイレの設置とは関係ないのですが、ハムスターの場合、ときどき爪が伸びすぎてしまう子が居ます。 自然界では巣穴を掘る、テリトリーの内外を走り回る(*1)といったことで爪が伸びすぎてしまうということはないのだろうと思いますが、飼育下では、巣穴は掘れない、走り回れるのはケージ内か室内ですから、爪の減り自体はコントロールされていないのではないかと思います。
この対策としては、なにか容器を入れてあげて、そこに目の粗い砂などを入れ、掘る欲求を満足させてあげる(実際用を足すでもなく、ハムスターたちは勢い良く砂を掘ることがあります)というのがあります。容器を用意して砂を入れるのであれば、ということで、我が家では、トイレ砂を目の粗い種類にして、トレイと砂場とを兼用してもらっています。
2.容器にはどんなものを使うか?
さて、ハムスターのトイレに使う容器ですが、市販のものを含めていろいろあります。 市販されているものだと、三晃商会のミニレットTMや、コーナーに置くタイプのトイレ容器(ハムレットTMなど)などもあります。 これらを使うのはなかなか楽でよいかも知れません。 ハムスターの覚えも良いように思います。
他に使えるものとしては、小鳥の水浴び用の容器があります。 小判型をした瀬戸物の容器に、トイレ砂を入れてあげればOKです。 また、小判型ではなく、いわゆる「角バス」といわれる、四角いタイプの容器もあります(右の写真を参照)。うちでは、角バスの「大」を愛用しています。
(1)大きさはどのくらいがよい?
トイレの大きさは、ハムスターの種類によって変えた方がよいと私は思っています。 それは、基準となるのがハムスターの体の大きさだからです。 ゴールデンハムスターの場合、トイレ容器に同じ角バスを使っても、特大の長辺が23cm近いものを設置すると、そこは巣箱になってしまうことが多いのです。逆に小さすぎると、ハムスターが入れなかったり、入れたとしても、お尻をあげたときに縁からはみ出して、トイレの役をしなくなってしまったりします。 ちょうど良いのは、ハムスターが中に入った時に、前後左右にそれぞれ1cm程度までの余裕があるくらいの大きさのようです。
ただし、トイレとして使ってくれるかどうかは、覚えてもらったときの大きさで決まりますから、初めに設置するときに注意が必要です。 トイレの場合には、一度トイレ容器だと認識してもらえれば、その後のずっとトイレとして使ってもらえる確率はかなり高いです。
(2)形はどんなものがよいか?
トイレ容器の形には、一定の条件があるようです。 ハムスターが入って落ち着くためには、まず、縁が床し高くなっていること、次に、ハムスターが中でくるくる回れる空間があること。そしてあまり広すぎないこと。 砂の有り無しは、一度覚えると関係ないようですが、あまり汚れが進むと、ハムスターもトイレを放棄して、他の場所で抗議のおしっこをする場合がありますから、こまめに掃除してあげて下さい。
また、屋根の有り無しもあまり関係がなく、むしろ縁の高さがハムスターが自然にしているときに、背中が隠れない程度の高さ、というのが結構キーポイントのようです。
トレイ容器を置かない場合には、ハムスターはケージの隅や巣箱と壁との間など、狭い隙間で壁が直角に交差した場所をトイレにする傾向があります。 従って、トイレ容器のの中に、そういった条件を満たす場所があることが必要ですから、真円形の容器などは(試したことがないですが・・・)向かないのではないかと思います。
3.砂にはどんなものを使うか
ことトイレの砂に関しては、一概にどんなものがよい、どんなものはいけないというものは、今のところないように思います。 ここでは、私が考えていること(従って、科学的根拠は希薄ですし、また、偏った内容)を述べたいと思います。
うちで使っているのは、猫用のシリカゲル(商品名:シャトル,シリカサンド など)です。 これを使うのは、単に吸着能が大きく、脱臭効果が持続するからではありません。
(1)紙製の砂はどうか?
たとえば、紙製の砂(トイレ材)を使う場合に考えなければならないのは、それが濡れたときにどうなるか、ハムスターが運ぼうとするか、ハムスターが運ぼうとするとして、その時どうなるか・・・です。 紙製の砂の場合には、溶けて固まるタイプと溶けないしかたまらないタイプの二通りがあります。 うちでもしどちらかを使うとすれば、溶けないしかたまらないタイプです。 理由は、ハムスターが頬袋に入れて運ぶからです。 固まらないタイプの場合には、繊維がほぐれてぼろぼろになるにはある程度以上の時間を要しますが、溶けて固まるタイプの場合には、固まるために繊維がほぐれやすくなっています。 ハムスターはセルロースそのものを消化するわけではありませんので、頬袋で、ほぐれた繊維は問題になります。
(2)木製の砂はどうか?
次に、木製の砂はどうかというと、これも固まるタイプとかたまらないタイプがありますが、うちではどちらも使いません。 ハムスターが食べてしまう(実際には囓っているだけのようですが)という話しもありますし、やはり巣材として運ばれてしまう可能性があること、ケージ1で述べたようにウッドチップへのアレルギー(ハムスターも人間も)が気になることなどから、木製のものは使いたくないなぁと思っています。 以前、シリカゲルのものが手に入らずに、仕方なく木製のを使ったら、トイレで用を足さなくなってしまった子も居ました(あくまでもうちの場合 です)。
(3)鉱物性の砂は?
さて、残ったのが鉱物製ですが、これにも固まるタイプと固まらないタイプがあります。 紙製の場合と異なるのは、鉱物性の「固まる」は、溶けて固まるのではなく、水分を吸着したときにとけ込んでいた成分が析出して、固結が起こって固まるか、または、表面エネルギーの変化の差分を、表面張力で補うために粒子同士が結びついて固まっている点です。 従って、この場合には、適度の水分が供給されると元通りバラバラの粒子に戻ります。
もちろん、ハムスターが飲み込んだ場合の問題はあるのですが、ハムスターという動物、ああ見えて結構学習能力は高いようで、食べられない&役に立たないことを一度学習すると、以後、囓ったり運んだりはしなくなるようです。 紙製の砂の場合には話が違って、感触から、巣材に使えるという認識になってしまうようです。
(4) なぜシリカゲルか?
なぜその中からシリカゲルを選んだかというと、成分が単純で、多量に摂取しない限り、また、微粉末でない限り無害であることが分かっている(シリカゲルを販売しているメーカーさん、といっても、猫砂のメーカーさんではなく、試薬として売っているメーカーさんのMSDSを取り寄せれば分かります)からです。 他のものでも、食品添加物に同様の鉱物が使われているものなどもありますが、成分が単純(SiO2)で理解しやすい点で、うちではシリカゲルを用いています。
ただし、同じシリカゲルでも、お菓子の乾燥剤などに入ってくる青いやつは、吸着性能を色で判断できるようにコバルトが添加されているし、そもそも保証外の使い方なので使ってはいけません。 をばしめ シリカゲル以外の表示のあるものは、鉄粉だったり 脱酸素剤だったりしますので、絶対に、開封したり、間違っても動物のトイレに入れたりしないようにして下さい。 いろいろな意味で大変危険です。
(5)砂の粒度は?(*2)
さて、最近では小動物用のシリカゲルも販売されています。 これを使うのもなかなか良いと思うのですが、我が家ではあえて猫用の粒度の高いものを使っています。
理由は、飲み込みが怖い のと、目などへのくっつきの頻度を下げたいからです。 粒が大きければ、ハムスターは、初めて接するものに対して、まず囓ってみてから、食べられるものであれば餌の貯蔵庫へ、巣材になるものなら寝床へ運ぶか判断し、運ぶ場合には頬袋に入れます。 小さいと、直接頬袋に入れてしまう場合や、いきなり臼歯で砕こうとする場合があります。 大きければ門歯でまず砕きます。 その際、食べられないもので、なおかつ頬や舌などの湿ったところにベタベタとつく(上で書いたように鉱物製の場合には、適度な水分が供給されればはがれるので、くっついても暫くすればはがれます)ので、食べられないし運べないことを学習するのです。 従って、できれば粒が大きい方がよいと思っています。 また、上で書いたように、爪を減らす為にも、球形で粒度のそろった小動物用よりも、あるていど粒度に分布を持っている(*3)猫用の方が適していると思っています。
4.ドワーフ種の場合は?
ドワーフ種(*4)の場合には、多少事情が変わります。 体が小さいだけでなく、トイレを認識してもらうのが難しいのです。 トイレと認識される条件が厳しいと言った方が正確なのかも知れませんが、ではなにが足りないのかと言われると、これがまた「?」なのです。
経験上、覚えてくれやすかったのは、容器はミニレットでも角バスでも、砂にミニクリーンTMを使った場合です。
その場合でも、数日で覚えると言ったことではなく、根気強く設置し続けているうちに、自然にいつの間にかそこでする事が多くなっていったという場合がほとんどです。
うちのばあい、ドワーフ種の飼育数がまだ少ない(*5)ので、これなら確率高く覚えてくれる という方法はまだ見つかっていません。
5.トイレを覚えてもらうには・・・
ゴールデンハムスターは比較的簡単にトレイを覚えてくれると言われています。 ここでは、ゴールデンハムスターの場合について、我が家で行っているトイレを覚えてもらう方法について記します。
(1)設置場所は?
上でも書きましたが、トイレの設置場所はハムスターが落ち着ける場所が良いです。 我が家では、ケージの4隅のうち一つに置いています。 真ん中に置いてもトイレとして使ってくれる場合もあるのですが、ケージの中のものの配置が苦しくなってしまいます。
(2)すぐに覚えてくれない?
里子でもらってきたハムスターで親がトイレを覚えていた場合や、ショップに居るときからトイレを使っていたハムスターでは、すぐにトイレを使ってくれることが多いのですが、とくにショップ出身のハムスターで、成長している場合にはなかなか覚えてくれず、トイレ容器以外の場所で用を足してしまう事が少なくありません。
このような場合には、おしっこで汚れた敷き材をまずトイレ容器に入れ、次にトイレ容器を用を足している場所に移動します(うちでもトイレを覚えるまでは、新聞紙を平らに敷くなどの敷き材を使います)。 1回で覚えてくれなくても、これを数回繰り返すうちにトイレと認識してもらえるようになるはずです。
稀に、トイレ容器を巣箱と認識してしまうハムスターが居ます。 この場合には、あきらめてもう一つ、巣箱になってしまったものより一回り小さい容器をトイレ用として入れてあげて下さい。
(*1) ゴールデンハムスターのテリトリーは数10m四方といわれていますが、行動半径は数kmに及びます (もどる)
(*2) 粒度とは、粒の大きさを科学的に表現する言葉です。 大きいときには粒度が高い、小さいときには粒度が低いと言います (もどる)
(*3) 分布を持っている というのは、大きさのちがうものが混ざっているということです。 粒度に分布がないというのは、同じくらいの大きさのものばかりで構成されていることを指します。 (もどる)
(*4) ここで言うドワーフ種には、 ジャンガリアン、キャンベル、ロボロフスキーに加え、チャイニーズも含みます。 (もどる)
(*5) うちでは、これまでにゴールデンは50匹ほどおつきあいしましたが、ドワーフ種は10匹とまだまだ経験が少ないのです。(もどる)
(*6) エージレスR は 三菱ガス化学(株)の登録商標です。 ミニレット,ミニクリーンは三晃商会(株)の商標です。 その他商品名は各社の商標です。(もどる)